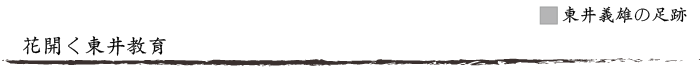
| 1957年 (昭和32年/44歳) |
10年間の沈黙を破った、いわば戦後の処女作であり不朽の名著ともいわれる『村を育てる学力』を発表する。(当記念館にて販売中)この著書は、東井が谷あいの小さな貧しい村(少年時代の母校)で、子どもたちをど真ん中にすえながら、農民の生き方そのものを問いなおしていく実践の記録である。また、生活の貧しさのために心まで貧しくなってしまっている村の子どもたちに、何とか『村を育てる学力』を、こんなくらしは自分1代だけでもうたくさんと、子らには都会で暮らすことを夢見させる大人たちに何とか生きがいをと、なお、自らも敗戦の衝撃から立ち上がるための命がけの実践記録であるともいえる。 | ||
 『村を育てる学力』を出版する 『村を育てる学力』を出版する |
|||
| 1959年 (昭和34年/46歳) |
「ペスタロッチー賞」を受賞する。
僻地にあって、常に綴り方教育に情熱を傾けると共に『村を育てる学力』『学習のつまずきと学力』等々に示したすぐれた実践と理論に対する功績により広島大学より「ペスタロッチー賞」を受賞する。 |
 相田小学校の子どもと |
|
| 終生子どもと共にありたいと願う東井であったが病気休職の校長の後をついで、相田小学校長におしあげられる。 | |||
| 1961年 (昭和36年/48歳) |
但東町立高橋中学校長に就任する。 | ||
| 1964年 (昭和39年/51歳) |
八鹿町立八鹿小学校長となる。 | ||
| 全国から学校参観者が訪れる毎日で、ここでの8年間が教師として名実ともに最も充実した時代であったといえる。 | |||
| 後日発刊される東井義雄著作集別巻『培其根』は、この時代に校長として教職員を個別指導した記録である。 | |||
 八鹿小学校の子どもと |
 校長室で |
||
| 東京オリンピック開催 | |||
| 1967年 (昭和42年/54歳) |
『通信簿の改造―教育正常化の実践的展開』を発刊。 | ||
| 時にはギロチンの役目を果たすことになりかねない形式的な5段階の通信簿の改訂に学校ぐるみで取り組み、「光を見てやろう、そして天一ぱいに、星をかがやかせよう」と一人ひとりの子どもの光を、この上なく大切にした実践記録の1つである。
「一番より尊いビリだってある」これは東井が師範学校時代自らの体験から得た教育信条である。 「どの子も子どもは星」これは東井が55年の教育生涯の中で最も大切にした教育信条である。 |
|||
|
『どの子も子どもは星』 |
|||
| 「東井義雄詩集」より | |||
| 略歴 | 少年期〜青年期 | いのちの教育に目覚める | 苦悩の時代 | 花開く都東井教育 | 仏の声を聞く |
 東井義雄著『村を育てる学力』
東井義雄著『村を育てる学力』