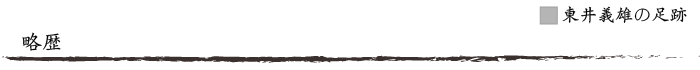| 1912年 (明治45年) 4月9日 |
兵庫県出石郡合橋村(但東町)佐々木の東光寺の長男として生まれる。 少年期から青年期 | ||
| 少年期〜 青年期 |
1918年 (大正7年) |
小学1年生のとき、母と死別。 | |
| 1923年 (大正12年) |
苦学し小学5年生で中学(旧制中学)入試資格試験に合格するが、貧しさのため父の許しが出ず、諦める。 | ||
| 1927年 (昭和2年) |
「一番安く学べる学校」という理由で、師範学校(姫路)に入学。 | ||
| 1932年 (昭和7年) |
師範学校を卒業、豊岡市豊岡尋常高等小学校に着任。以来10年間在職。 いのちの教育 | ||
| いのちの教育 | 1935年 (昭和10年) |
多くの論文を発表、綴方教育界でその存在を認められるようになる。 | |
| 1938年 (昭和13年) |
加藤富美代(城崎郡日高町生まれ)と結婚 | ||
| 1938年 (昭和13年) |
父と死別 | ||
| 1941年 (昭和16年) |
愛児の大病 | ||
| 苦悩の時代 | 1942年 (昭和17年) |
故郷の合橋村立合橋国民学校に転勤 苦悩の時代 | |
| 1944年 (昭和19年) |
合橋村立唐川国民学校に転勤 | ||
| 1945年 (昭和20年) 敗戦 |
1947年(〃22年) 相田小学校(小学校時代の母校)に転勤。14年間勤務する。 | ||
| 1959年 (昭和34年) |
相田小学校長となる。 | ||
| 「ペスタロッチー賞」を受賞 花開く東井教育 | |||
| 1960年 (昭和35年) |
「小砂丘忠義賞」を受賞 | ||
| 1961年 (昭和36年) |
但東町立高橋中学校長となる。 | ||
| 花開く 東井教育 |
1962年 (昭和37年) |
神戸新聞社より「平和文化賞」を受賞 | |
| 1964年 (昭和39年) |
八鹿町立八鹿小学校長となる。 | ||
| 1967年 (昭和42年) |
兵庫県知事より「教育功労賞」を受賞 | ||
| 学習研究社より「学研教育賞」を受賞 | |||
| 1971年 (昭和46年) |
文部省より「教育功労賞」を受賞 | ||
| 1972年 (昭和47年) |
定年退職。40年間に渡る教員生活を終える。 仏の声を聞く | ||
| 1973年 (昭和48年) |
退職後1年は八鹿町社会教育指導員となるが、その後、姫路学院女子短期大学講師。 | ||
| 続いて兵庫教育大学大学院非常勤講師を兼務し、教育活動を続ける。 | |||
| 1981年 (昭和56年) |
但東町より「教育特別功労賞」を受賞 | ||
| 仏の声を聞く | 1982年 (昭和57年) |
内閣総理大臣より「勲五等双光旭日賞」を受章 | |
| 1987年 (昭和62年) |
検査入院の結果、胃ガンと診断され、入院。胃部の三分の二を切除。 | ||
| 1988年 (昭和63年) |
「正力松太郎賞」を受賞 | ||
| 1991年 (平成3年) 4月18日 |
豊岡病院にて逝去 | ||
| 内閣総理大臣より叙位、従五位に叙せられる。 |
| 略歴 | 少年期〜青年期 | いのちの教育に目覚める | 苦悩の時代 | 花開く都東井教育 | 仏の声を聞く |