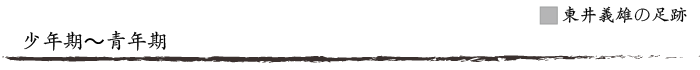
| 1912年 (明治45年) |
兵庫県出石郡合橋村(但東町) 佐々木の寺(浄土真宗本願寺派東光寺)の長男として生まれる。 | ||
 幼少の頃の東光寺 |
父(義證)が大谷本廟務めであったため、三歳までは京都で過ごす。 |  生後6ヶ月 生後6ヶ月 |
|
| 1918年 (大正7年/6歳) |
小学1年生のとき、母(初枝)と死別する。 この時の悲しみ・寂しさを後年次のように記している。 |
||
|
父が不在の時など、母が仏前に座しておつとめをする時そのかたわらで、 |
|||
| 1923年 (大正12年/11歳) |
うどん箱を机がわりに勉学に励み、小学5年生で中学(旧制中学)入試資格試験に合格するが、貧しさのため父の許しが出ず、諦める。 | ||
| 関東大震災 |  師範学校時代 師範学校時代 |
||
| 1927年 (昭和2年/15歳) |
どうしても進学の夢は捨て切れず、「一番安く学べる学校」という理由で、師範学校(姫路)に入学。 師範学校では全員が何かの部に入らなければならず、東井はマラソン部に入部する。 しかし、運動の苦手な東井は卒業するまでビリを走りつづけた。ビリを走りながら東井は、「先生になったら運動でも勉強でもビリッ子の心が分かる先生になろう」と決心した。 |
||
| 1928年 (昭和3年/16歳) |
師範学校2年生の時、漢文の宿題で『独来独去無一随者』のことばに出会い、衝撃を受ける。 「母はとっくに行ってしまった。父もやがて行ってしまう。私もいつか一人ぼっちになる日が来る」この不安から逃れようと、関係書をむさぼるように読む。 心の遍歴は、既にこの頃から始まる。 |
||
| 略歴 | 少年期〜青年期 | いのちの教育に目覚める | 苦悩の時代 | 花開く都東井教育 | 仏の声を聞く |